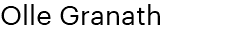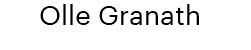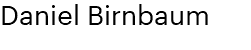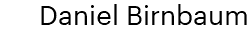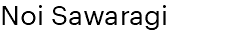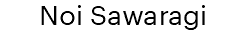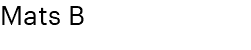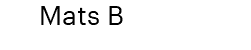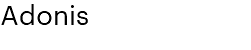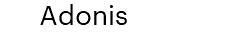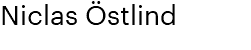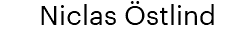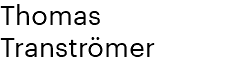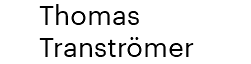椹木野衣 美術と時評 73:マドハット・カケイの絵画と流浪・円環、そして偶然
連載目次

マドハット・カケイの作品(無題) 「マドハット・カケイ 個展」(阿久津画廊、前橋、2017年)での展示風景 撮影:筆者(以降すべて) Courtesy Madhat Kakei
知人の若い建築家の紹介で、ちょうどその時期に前橋で個展を開催中のクルド人画家がいることを知った。名をマドハット・カケイという。「カケイ」とは日本人みたいだが、日本との血縁はない。ゾロアスター教の流れを汲む信仰を持つクルド人のあいだではよくある名らしい(イラク生まれの彼は、もとはアラビアン・ネームのマドハット・モハムッド・アリを名乗っていたこともあるようだ)。ゾロアスター教は拝火教とも呼ばれるとおり、火の儀礼と深いつながりがあるから、漢字で「火系(カケイ)」と当て字することもできそうだ。これは単なる偶然の戯言だが、偶然といえばひょんなことからカケイはマドリードで知り合った日本人の友人との縁を得て来日。以来、日本とヨーロッパを行き来するようになり、かなり前から千葉市のはずれの緑豊かな一角に古い診療院を改装した情緒ある共同アトリエ「翔青館」を構えている。もっとも、ここが主というわけではない。カケイはほかにヨーロッパでは北欧のストックホルムとパリの郊外にもアトリエがあるそうなので、世界3ヶ所に自分の創作の場所を持っていることになる。こういうことは世界がグローバル化した現在ではさしてめずらしくもないのだろう。だが、彼の場合はいささか事情が違っている。
1954年に生まれたカケイの故郷はイラク北部に山岳地帯を控える「クルディスタン」と呼ばれる広大な領域で、近代の枠で言えば「国」ではないが、そのはるか前から多くのクルド人が暮らしてきた事実上の母国である。この複数というのがとびきりで、イラクのほかにトルコ、イラン、シリアそしてアルメニアの一部もクルディスタンだというから、どこも深刻で複雑な多民族的な背景を持ち、長く近代的な国家の枠組みや国境の線引きと対立してきた(もう少し北に昇ればあのスターリンの生まれたグルジア-現在の読みではジョージア-で、ここはのちにキリストの「血」となるワインの原郷として知られている。そういえばカケイの髭はスターリンを思わせもするが、容貌はゾロアスター=ツァラトゥストラによる一大反キリスト教放浪譚を筆したニーチェを思わせる)。

マドハット・カケイ
とりわけカケイが生まれたイラク北部のキルクークは国内でも有数の石油産出地帯が位置することなどから、クルディスタンは複雑な地政学的位置にあり、かつてサダム・フセインが化学兵器による抵抗勢力の虐殺を行った地としても知られている。そういう事情から、イラク戦争でアメリカ軍がフセインの排除に成功すると、クルド人による独立の機運が高まり、現在ではこの地を含むクルディスタン地域は独自に自治政府を形成している。昨年の9月25日には住民投票も行い、90%を超える圧倒的多数で独立賛成派の勝利を宣言した。しかしイラク政府は憲法の枠を逸脱する行為としてこれを認めず、周辺国もこの宣言に対して厳しい対応を取り、これに加えて各国政府やクルド自治政府とISIS(イスラム国)との抗争が幾重にも輪をかけ、緊張は今も高まる一方だ(*1)。
このように、クルド人をめぐる歴史的な背景について書こうとすれば、それだけでたちまち頁が埋まってしまう。それくらい、近代の枠組みのなかではとうてい捉え切れないほど古く、広大な地域に由来する民族的背景をカケイは持つ。しかもカケイは、バグダッドで絵の勉強をしたあと、マドリードの美術学校に留学したものの、帰国後の1980年代にイラン・イラク戦争が起き、イラク軍の兵士として戦争への参加を余儀なくされている。その主戦場は国境付近のクルド人居住区域にわたっていたから、二国間で徴用された兵士がクルド人同士ということもあった。「イラン」や「イラク」が成立するずっと前からこの地に住む同じ民族が、近代以後の枠組みを理由に殺し合うのに我慢ができなかったカケイは、意を決して軍を離脱。国境に広がる山岳地帯に身を隠し、イランからバルカン半島を経て、東欧から難民の受け入れに積極であった北欧スウェーデンへと逃げ延び、以来そこが母国に代わる仮の住まいとなった。いったい、カケイは難民なのだろうか、亡命者なのだろうか、それともコスモポリタンなのだろうか。どうも判然としない。そういう呼称自体が近代の産物にすぎないからだ。世界の三箇所にアトリエを置くことくらい、なんでもないことに違いない。
そんなカケイを日本で最初に評価した美術評論家は、針生一郎と洲之内徹だった。二人とも私が大きな影響を受けた数少ない美術批評の先達だ。ちなみに建築家の磯崎新は、このカケイに頼まれ、クルド人のための現代美術館の設計に着手するため現地入りしたときの「迷走」について昨年、雑誌『現代思想』に興味深いエッセイ「アララット山」(新連載「瓦礫(デブリ)の未来」第1回、2017年8月号)を寄せているが、その冒頭で、カケイを紹介されたのはイラク戦争後に針生一郎からのことだったと書いている。他方、いま私の手もとにある『芸術新潮』1987年9月号は洲之内が連載「気まぐれ美術館」で最後に画家を紹介した回(第163回「誤植の効用」)に当たっている。針生が扉文「マドハット・モハムッド・アリの版画」を寄せたフォルム画廊での個展が開かれたのは1988年11月だから、1986年にカケイが来日してから、二人とも立て続けにカケイに関心を示したことになる。針生一郎、洲之内徹、磯崎新(先のエッセイで磯崎は、ノアの方舟が漂着したとされるアララット山をめぐる洪水伝説について触れているが、拙著『震美術論』で私もまた磯崎の先祖が地震で別府湾に沈んだとされている瓜生島の伝説に章を割いている)となれば、ある意味、この文章の冒頭で書いた、やはり磯崎と縁のある若い建築家の紹介でカケイのことを知り、前橋の小さな画廊を訪ねたのは、もはや偶然ではないように思えてくる。
アーツ前橋と前橋文学館で「ヒツクリコ ガツクリコ ことばの生まれる場所」展を見に行ったその日、日本語(意味)とイメージ(無意味)が交錯する場所=非場所について考えながら、私はカケイの個展が開かれている前橋駅に近い小さな画廊を訪ねた。ここでの個展はすでに6回目とのことだったが、この日が最終日だった。部屋に入ると、すぐにカケイとわかる人物がいた。そして絵を見ながら、おのずと会話は始まった。カケイの英語は流暢ではないが饒舌だ。そのうち針生や洲之内が寄稿した文章を出してきて見せてくれた。洲之内は千葉のアトリエにも足を運んだらしく、その時の写真もあった(翌月、カケイがストックホルムに戻るこれまた滑り込みの前日に、洲之内が足を踏み入れたのと同じそのアトリエに私も足を運ぶことになるとは、その時はまったく思っていなかった)。磯崎のエッセイの話もした。するとカケイは磯崎が訪ねたと書いていたクルド人のための現代美術館の建設予定地の写真も見せてくれた。乾いた土地がどこまでも続いていた。まさかここが、世界を丸ごと呑むほどの洪水さえ凌いだアララット山へと続く、かつて水没したとされる土地の途上であったとは。
肝心のカケイの作品について触れるのが遅れてしまった。それくらいカケイをめぐる状況は複雑怪奇なのだ。しかし、かんたんには解きほぐすことができない何重にもわたるこうした多層性は、まちがいなくカケイの絵に大きな影を落としている。正面からパッと見たとき、あるいは印刷などを通じて見るカケイの絵は、どこにでもありそうなモノクロームの絵画に見える。しかし実物の前に立って見れば、それが数え切れないくらい淡い階調が下地から透過して目に届く、無限と言ってよい確率論的な効果(=無意味)を脳が意味(色)として束ねた結果にすぎないことがはっきりとわかる。視野が無際限に揺らぐようなこの効果は、いったいなにに由来するのだろうか。絵の縁を見てわかった。モノクロームの画面に見えたのは、実は何層にもわたって分厚く塗り重ねられた絵具の層を垂直方向から透視した切断面だったのだ。

この手法自体は、洲之内が気まぐれ美術館で触れたその頃の墨一色の木版画や即興性の高い襖絵とはかけ離れているし、1998年に銀座のギャラリーKでの個展(ほか前橋、千葉、鹿児島、コペンハーゲン、ストックホルムで開催)の際に作られ、やはり針生が寄稿し日英バイリンガルで編集された冊子(針生のほかにシリアの著名な詩人アドニスがカケイの絵へのオマージュを捧げている!)を見ると、同じモノクロームの特徴は備えているものの、色調が今とはまったく異なる。現在のカケイの画面は、光り輝くように鮮やかな特徴を持ち、見る者の網膜に太陽の残像のように長く消えない余韻を残す。多層に重ねられた異なる色層の予期せぬ混ざり合い(=過去)が、結果として一見しただけでは均質そうに伺える表面(=現在)を作り出している。それが、過去から未来へと向けてカケイがたどってきた個人と民族のはざまで休みなく繰り広げられる、永劫の流浪と根源への回帰の共存に物質的に対応するものであることは言うまでもない。

翔青館(千葉)内にある、カケイのアトリエにて
翔青館での別れぎわ、もう一度、洲之内の話になった。私が「今年は、洲之内が死ぬならこの場所でと決めていた新潟の小さな山荘が今も残っているかどうか、晩年の洲之内と交流の深かった美術批評家、大倉宏さんに案内してもらい訪ねてきた」と話すと、「私もそこに行ったことがある!」と躍り上って喜んだ。そのとき、山荘は雑草が腰上まで生い茂る斜面の一角に埋もれ、傍からは姿かたちさえ臨むことができなかったが、私たちは遠回りをして斜面をなんとかよじのぼり、付近へと接近した。すると、あった。雨風で朽ちてはいるものの、実に洲之内らしい佇まいで「終のすみか」はまだ残っていた。そのことを話すと、カケイは心から嬉しそうに微笑んで固く握手をした。そうだ。カケイは洲之内が「気まぐれ美術館」で取り上げた「最後の=終の画家」なのだ。そういえば、その洲之内の終の住処を訪ねる奇妙な旅に同行していたのは大倉のほか、別府から新潟に来ていた高橋鴿子(はとこ)だった。彼女もまた洲之内の「気まぐれ美術館」で画家、佐藤溪を知り、佐藤の絵を集め、由布院に美術館まで建て、運営が難しくなってやむなく閉館を決めた矢先に私が別府を訪ね、たまたま知り合ったのだった。ちょうど彼女は、新潟の砂丘館で開かれていた映画監督、佐藤真の展覧会で私が話をするのを聞きに、別府からやってきてくれたのだった。その佐藤もまた、洲之内の美術評論を読み、もう二度と後戻りできぬほどの強い影響を受けた人物だった。私は針生とは晩年、親しくやりとりをさせてもらったが、洲之内とは会ったことはない。しかし批評は何度でも蘇る。クルディスタンと千葉と新潟を新しい縁で繋ぎ、ニーチェのいう永劫回帰がそうであるように、四方八方に予期せぬ偶然と必然を産み落としながら。
*「マドハット・カケイ展」は2017年11月18日~2017年11月26日、阿久津画廊(前橋)で開催された。
1. 「『空港返せ』『油田返せ』イラクと周辺3カ国が独立反対で四面楚歌のクルド人」、『ニューズウィーク日本版』(ウェブサイト)2017年9月28日、株式会社CCCメディアハウス
著者近況:1月27日、審査員を務めた『第6回札幌500m美術館賞グランプリ展』初日のシンポジウムに登壇予定。2月18日、横浜美術館『石内都 肌理と写真』展関連イベントとして、映画『ひろしま 石内都・遺されたものたち Things Left Behind』上映のポストトークに参加(石内および、同映画の監督リンダ・ホーグランドとの登壇)。2月23日、『北川フラムの対話シリーズ 知をひらく人たち 第6回「岡本太郎」』にゲスト参加。会場はクラブヒルサイドサロン(代官山)。
2018年1月17日 椹木 野衣
日本語
eng
|